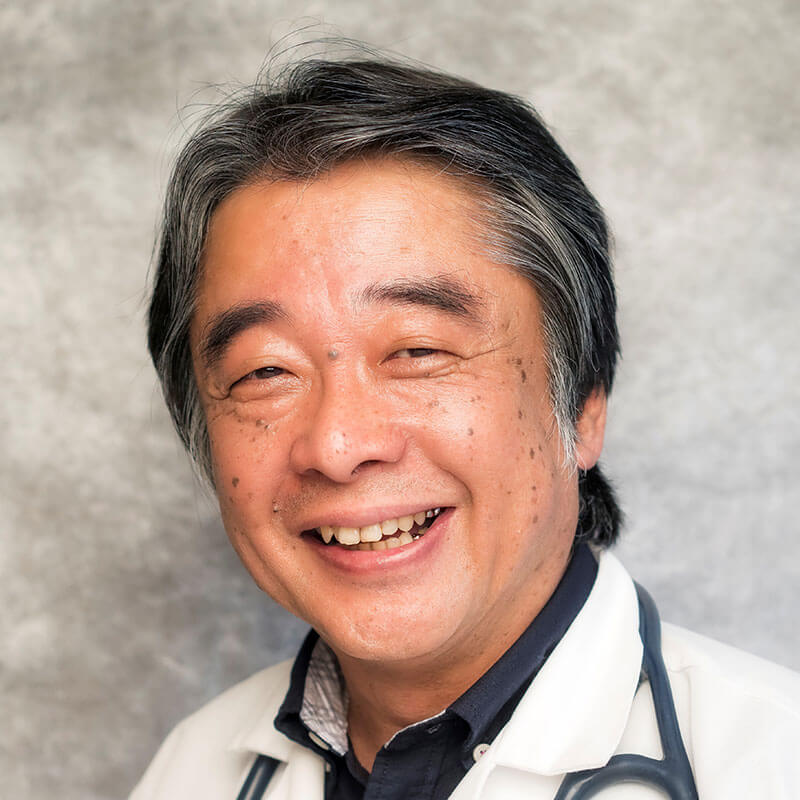キャンピングカーは、ペットと旅を楽しみたい人にとって非常に有効なツールです。日本RV協会が発行する「キャンピングカー白書2022」のアンケートでも、回答者の約40%がキャンピングカー購入のきっかけを「ペット」と答えています。
ペット連れユーザーの中でも大半を占めるのが、犬と一緒にキャンピングカーで旅行やキャンプを楽しんでいる人。そこで今回は、公益社団法人日本獣医師会 副会長 村中志朗先生(広尾動物病院 院長)にお話を伺い、犬を連れてキャンプや旅行をする際の注意点を2回に分けて紹介します。
第1回は、ドライブ時、熱中症対策、トイレ、食事などの注意点。ペットと旅を楽しむキャンピングカーユーザーには大変役立つインタビュー内容ですので、ぜひ最後までじっくり読んで自身のペット旅の参考にしてください。

目次
①ドライブに慣れさせる

まず、「犬がドライブに慣れている」ことが大切です。犬を連れて遊びに行く際は、不快な思いをさせないことが大前提。クルマに慣れていない犬だと、移動中にぐったりしたり、吐いてしまうなど、様々な問題が起こります。たとえエアコンが効いていても、不安からくる過呼吸が体温を上げてしまうので、適切な車内温度でも熱中症は起こりえます。クルマに乗ったときに不安を感じてハァハァと荒い呼吸が止まらないような犬は、連れて行かないことが原則です。
犬をクルマに順応させるには、最初から長時間の移動ではなく、季節のいい時期に普段からちょっとしたドライブをして慣らすのがいいと思います。その際は、買い物などで車内に放置をするような状況はもちろんNGです。そばに飼い主がいることで不安が解消されるので、小型犬なら最初は飼い主の膝の上に乗せるのがいいでしょう。運転手とは別の人の膝の上で「怖くないんだよ」ということを教えてあげて、クルマに対して悪い印象を与えないことが大切です。
犬にもそれぞれ性格がありますから、クルマがどうしてもダメな犬は動物病院で酔い止めを処方してもらいましょう。犬の酔い止めは、いわゆる精神安定剤です。犬のクルマ酔いは不安からくるものですから、薬を使ってそれを解消してあげる。クルマの移動時間を伝えれば、先生がそれに合った薬を処方するでしょうし、薬を飲ませるタイミングの指示もあると思いますので、その指示に従って薬を飲ませてください。帰りのことも考えて、往復分の薬をもらっておきましょう。
こうしたケアができないのであれば、嫌がる犬を絶対に連れて行ってはいけません。それは人間の勝手であり、犬にとっては迷惑でしかないからです。
②走行中の転倒防止

現在はペット用のカーグッズがたくさんそろっているので、そうした商品で体のサイズに合ったものを選んでやることが第一です。小型犬ならキャリーバッグに入れておけば、急ブレーキを踏んだとしても大きな怪我は避けられます。膝の上に抱っこしていないと精神的に安定しない犬は仕方ありませんが、その場合は急ブレーキで犬が飛んで行かないように飼い主が配慮しなくてはいけません。
犬をクルマに乗せる際の基本は、安全のために転倒防止策をとっておくことです。大型犬の場合は、後部のシートを倒して広いスペースを作る。その際、飼い主が乗っているフロントシート後部にネットや柵を付けておくと、犬が「ここは行っちゃダメなんだ」とあきらめますので、落ち着きやすい環境作りに有効です。また、立っている状態から転倒すると大きなケガにつながるので、伏せができるスペースは必ず確保しておきましょう。
ドライブ中にキャリーやケージの中で落ち着いて過ごすには、普段からそこに入って移動することに慣らしておくのが大切です。キャリーやケージの中でおとなしくできることは、キャンプや旅行に限らず災害時にも役立ちます。クレートトレーニングを日頃からやっておかないと、いざ災害が起きた時、避難がスムーズにいかず二次災害につながったり、避難所での生活が困難になる可能性もあります。そういった意味でも、普段からキャリーやケージに慣らしておくことはとても重要です。
③熱中症・パッド熱傷の防止
夏場のお出かけでは、車内の温度管理がとても重要です。人間が快適に過ごせる温度であれば基本は問題ありませんが、第1章でもお話しした通り、重要なのは犬がクルマに慣れていること。クルマに慣れていない犬だと、車内が適温でもストレスからくる過呼吸で体温が上がって、熱中症になることがあります。
犬が過呼吸になると、ハァハァと音が出るような荒い呼吸が止まらなくなります。「呼びかけても反応がない」「水をあげてもまったく飲まない」などの症状を経て、最終的には意識がなくなって、すぐに処置しないと死に至ることもあります。異常な過呼吸時は、意識が半分飛んでいる状態。名前を呼びかけても荒い呼吸が止まらず、ぐったりしてしまったら、かなり危険な状態だと思ってください。
異常な過呼吸が見られる場合は、コンビニなどで氷や保冷剤を買って体を冷やすか、濡れたバスタオルで体全体を覆ってやる。それだけでも体温が下がるので、全然違います。アイスノンや氷で体を冷やすときは、脚の付け根や首筋などの大きな血管が通っている部分を冷やすのが効果的です。犬の状態に異常を感じたら早めにこうした処置を行い、それでもなかなか症状が収まらない場合は、すぐに動物病院に連れて行ってください。
エアコン付きキャンピングカーの留守番

エアコンを止めた車内に犬を置いて、飼い主が買い出しに出かけている間に熱中症で死んでいたとか、そういうことは絶対にあってはいけません。買い物や食事、入浴といった短時間の留守番でも、誰か1人残ってエアコンで車内温度を適温に保ってやることが原則です。
ただし、エンジンを止めた状態でエアコンを使用できるキャンピングカーであれば、家でエアコンをつけて留守番をさせておくのと同じことですので、基本的には問題ないと思います。もちろん、「犬がキャンピングカーの環境に慣れていて、車内に残しても落ち着いていること」「エアコンが途中で止まったりせず、確実に温度管理できること」が大前提です。
家と違う場所だと興奮しやすい犬は、留守番中に過呼吸を起こす可能性もあるので、そうした場合は人が残って付いてやる必要があります。どうしてもそれができないのであれば、ペットホテルや動物病院など環境の整った施設に犬を預けてください。
パッド(足の裏)の熱傷に注意!

真夏のアスファルトの温度は45~50℃くらいになりますので、炎天下に犬を歩かせると足の裏(パッド)をやけどしてしまいます。また、真夏の海では砂浜がかなり高温になっていますので、犬を炎天下の浜辺に出すなんてもってのほかです。
とくに暑さに弱く熱中症になりやすい犬種は、パグ、シーズーなど鼻が短い短頭種。解剖学的構造がほかの犬種とまったく違って、呼吸がしにくい構造になっているので、夏場の車内や屋外ではかなり注意が必要です。
犬が汗をかくのは、パッドの裏などごく一部だけ。基本は、冷たい空気を吸って体を冷やしてそれを吐く「呼吸」によって体温調整をしています。そのため、外の空気が体温よりも高いと呼吸をしてもまったく体温が下がりません。犬の体温がだいたい38~39℃くらいですので、外気がそれ以上になるような環境に出すというのは、考えただけでもゾッとします。屋外でも海や川、湖なら、水の中で遊べば体が冷えるし、体に水をかけてやるだけでも体温が下がるのでいいですが、浜辺や岩場など高温の場所は要注意です。
高速SAやキャンプ場での注意点

普段の散歩でも旅行でも、気温が30℃以上の暑い日にアスファルトの上を歩かせるのは危険です。地面が熱くて手で触れないような状態だと、当然犬の足の裏も熱いということ。最近ではドッグランを完備した高速道路のサービスエリアも増えていますが、炎天下ではアスファルトの上を歩かせず、ドッグランまで抱っこして移動するようにしてください。
キャンプ場の芝生や草地は、アスファルトのような輻射熱(照り返し)がなく、そこまで温度が上がらないので、キャンプサイトで過ごすこと自体は問題ありません。夏場はタープなどで日陰を作って、犬が過ごしやすい環境を整えてあげてください。アウトドア用ベッドやベンチ、チェアなどで、地面から離れた場所に犬のスペースを作ってやることも有効です。地面が芝や草地の場合はそこまで熱くならないので、あまり神経質になる必要はないと思います。
④旅先でのトイレ対策
キャンプや旅行は屋外での活動なので、普段から外でちゃんと排泄ができる犬の方が適応能力は高いです。なかには、散歩に行っても外で排泄せず、家のトイレでしか排泄しない犬もいます。ホテルに預けるにしても、動物病院に入院するにしても、散歩中に排泄をしないので室内で排泄させるしかない。そういう犬はトイレが変わると排泄しないことがほとんどなので、普段使っているトイレとペットシーツを必ず持参するようにしてください。
⑤食べ物・飲み物について

犬は環境が変化すると、ストレスですぐにお腹を壊して下痢をしたり吐いたりします。食べなれない物をあげると余計にお腹の調子が悪くなるので、最初からストレスによる下痢が起こるという前提で、普段食べなれた物を用意しておくのがいいでしょう。犬の中には、環境が変わっても平気な子もいるし、そうでない子もいる。自分の飼っている犬がどういう性格なのかを、普段から知っておくことも大切です。
食欲がない時はトッピングで対応
旅先で普段食べているフードを食べなくなるのは、環境が変わったことによるストレスが原因です。ストレスがあるから食欲も落ちる。だから美味しい物しか食べない。例えば、普段ドライフードを食べているのに、キャンプ場に行ったらドライフードを食べないという場合は、普段食べているものに缶詰やレトルトなどのトッピングを混ぜてやるのがいいと思います。
もちろん、何でもかんでもトッピングすればいいというわけではありません。慣れていない物を食べるとお腹を壊すので、必ず犬用のフードを用意すること。旅の期間にもよりますが、長旅だと栄養の偏りが出ますので、パッケージに「総合栄養食」と書かれている犬用フードを選んでください。総合栄養食系のフードであれば、栄養の偏りがないのでおやつとして多めに食べさせても問題ありませんし、ドライフードの食いつきが悪い時でもドライフードに混ぜて匂いと味を変えてやれば、たいがい食べるようになります。
キャンプではバーベキューをすることも多いと思いますが、犬が食べては行けない野菜や果物(タマネギ、ニンニク、ブドウなど)をあげないように注意しましょう。また、バーベキューの美味しいお肉を覚えさせるとドライフードを食べなくなってしまいますから、基本は犬用のフードを与えるようにしてください。
最後に、暑い時期はとくに水を欠かさないことが大切です。犬がいつでも飲める場所に、新鮮な水を置いておくことを心がけてください。もし水がなくなってコンビニなどで購入する場合は、マグネシウムやカルシウムの含有量が少ない「軟水」を選ぶこと。キャンピングカーはタンクに水をためてあるので、そういった意味では安心だと思いますが、飲み水以外にも暑いときに犬の体にかけて冷やすこともできるので、水は多めに用意しておくのがポイントです。
獣医師に聞く 犬と楽しむ夏のキャンピングカーライフの注意点②【害虫予防・緊急時の対応・マナーについて】